XOOPSとは
これまで運営していたWEBサイトはWordPressもありましたが、ほとんどがXOOPSで構築していました。
2007年頃に利用を開始し、当時は文字コードがShift-JISだった記憶があります。最初に使い始めたのはおそらく2.2以前のバージョンで、バージョン2.3からUTF-8が標準になったため、すべての文字コードを修正したことを覚えています。
当時はmixiの上場などを背景に「コミュニティサイトブーム」でした。XOOPSのほか、株式会社手嶋屋さんが公開しているOpenPNEやGeeklogなどのCMSも選択肢にありましたが、XOOPSは、海外の大学や有名サイトでの採用実績が多く、また関連書籍も豊富で情報を得やすかったため、採用を決めました。
Geeklogに関しては、明星大学で開催されたオープンソースカンファレンスに参加したこともあります(当時は多摩センターに住んでいたので、多摩モノレールで最寄り駅まで行きました)。久しぶりにGeeklogの公式サイトを開いてみたら消えており、衝撃を受けました。
当時のXOOPS
XOOPS本体のWEBサイトはいまも公開されており、GitHubを見ると定期的にメンテナンスも続いているようです。
ただし、日本国内では本家よりもローカライズ版であるXOOPS Cube Legacyが主流で、むしろ「日本におけるXOOPS=XOOPS Cube Legacy」という状況でした。
XOOPSは掲示板サイトに強みを持つCMSでしたが、搭載されていたのはあくまで基本的な機能のみ。そのため、追加モジュール(WordPressでいうプラグイン)を導入して拡張していくのが一般的でした。
当時よく利用していたXOOPS関連サイトの多くはすでに閉鎖されてしまいましたが、文系のためのXOOPS入門さんだけは今も残っており、とても懐かしい気持ちになります。
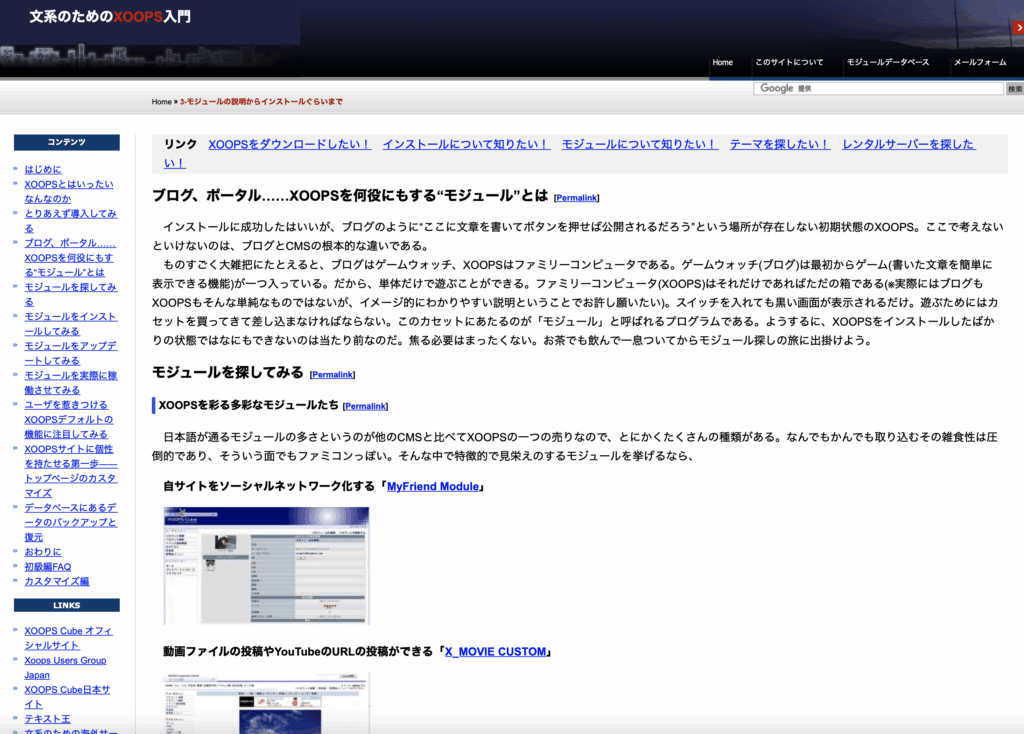
私自身もXOOPS Cubeで複数の掲示板サイトを運営していました。サーバー構成はWEBサーバー5台、DBサーバー2台という大規模構成で、当時はまだクラウドが存在せず、いわゆるオンプレ環境での運用でした。国内外にも事例がほとんどなく、独自に分散処理の工夫を重ねていたため、国内では最大規模クラスのXOOPSサイトを運営していたと自負しています。
XOOPSのモジュール
特にお世話になったのはGIJOEさんが開発されたモジュール群です。
掲示板モジュール d3forum
コンテンツ管理モジュール pico
権限管理モジュール altsys
セキュリティモジュール protector
これらの存在はXOOPS Cubeを大きく発展させる要因となりましたし、私自身も深く感謝しています。
もっとも、XOOPSはモジュールで機能を拡張できるとはいえ、細かい部分では痒いところに手が届かないことも多くありました。
例えば、ユーザー登録後の確認メールが届かないと、そのまま登録が完了しない仕様でした。そのため私自身で「登録確認メール再送信モジュール」を開発し、公式サイトに公開していたこともあります(現在は公式サイト自体が閉鎖され、手元にも残っていません)
新しいサービスを始めるにあたって
XOOPS本家は今も存在していますが、バージョンアップの頻度は落ちており、日本国内ではXOOPS=XOOPS Cubeという認識だったこともあり、いまの国内での情報はほとんどありません。CMSの選択肢としては、残念ながら現在では力不足と感じます。
現在の仕事ではWordPressを利用しています。情報発信の点ではWordPressがベストな選択肢だと思いますが、会員制サイトなど複雑な仕組みを構築する場合、Geeklogがなくなった今となってはDrupalが最有力のCMSだと考えています。
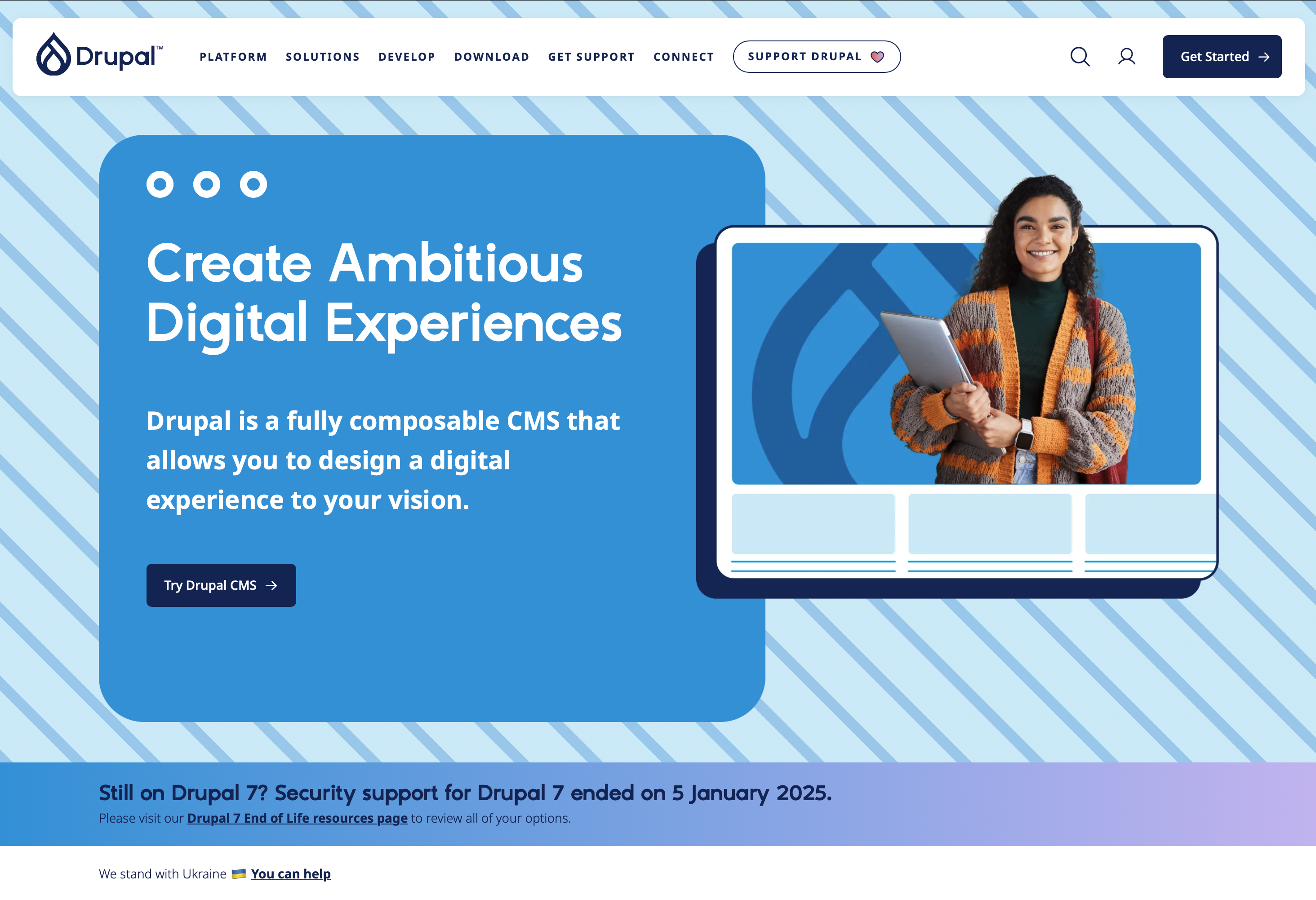
Drupalはメジャーバージョンアップが頻繁に行われ、ユーザーコミュニティでの情報交換も活発です。実際に少し触ってみると、XOOPSに慣れている自分には取っつきにくい部分もありますが、その分奥深さも感じます。
この1年は、このRIKKAサイトで情報発信を続けつつ、Drupalの知識を本格的にインプットしていきたいと思っています。

